公開日: |更新日:
掲載している治療法は保険適用外の自由診療も含まれます。自由診療は全額自己負担となります。症状・治療法・クリニックにより、費用や治療回数・期間は変動しますので、詳しくは直接クリニックへご相談ください。
また、副作用や治療によるリスクなども診療方法によって異なりますので、不安な点については、各クリニックの医師に直接確認・相談してから治療を検討することをおすすめします。
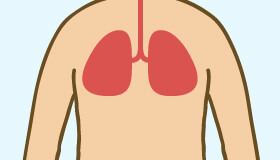
癌細胞が血液やリンパ液の流れに乗って離れた臓器に到達し、そこで成長することを転移といいます。肺には多くの血管やリンパ管が集まっているため、以下のように肺癌はさまざまな臓器に転移しやすいと考えられています。
(以下引用)
肺がんはリンパ節、反対側の肺、骨、脳、肝臓、副腎などに転移しやすく、特に小細胞肺癌では診断時にすでに転移しているケースも多く見られます。一般的に、転移した肺がんを手術ですべて取りきることは難しいため、症状がない場合は薬物療法を中心に、痛みなどがある場合は症状を取り除くための放射線治療や手術を行います。これらの治療ができない場合にも、症状を和らげる治療を行い、痛みや苦痛を緩和しながら日常生活を送れるようにします。
(以上)
肺癌は、特に進行が早い小細胞肺癌では診断時にすでに転移していることが多く、非小細胞肺癌でも脳・骨・副腎・肝臓などへの転移がしばしばみられます。また、早期であっても微小転移が起きている可能性があり、全身治療の必要性が重視されています。
骨に転移した場合、疼痛や骨折リスクがあるため、放射線治療や外科的固定術が行われることがあります。骨折予防として、ビスホスホネート製剤やデノスマブなど骨修飾薬が用いられることもあります。
脳に転移した場合は、症状の有無や転移の数・位置に応じて、手術・定位放射線照射(SRS)・全脳照射(WBRT)などが選択されます。無症状で小さい病変であれば、薬物療法が中心になることもあります。
肺癌では再発が肺以外の臓器や組織にも及ぶことが多く、全身に散らばった癌細胞を制御するために、薬物療法が治療の中心となります。非小細胞肺癌では、EGFRやALK、ROS1、KRASなどのドライバー遺伝子変異があるかどうかを調べ、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬を選択します。小細胞肺癌では、化学療法と免疫療法(アテゾリズマブやデュルバルマブの併用など)が標準治療に組み込まれています。
肺癌とは肺胞や気管、気管支の細胞がなんらかの原因で癌化してしまい増殖して発生します。
肺癌は周りの組織を破壊しながら進行し、血液やリンパの流れに乗って広がっていきます。組織やその集団の形の違いがあり、大きく小細胞肺癌と非小細胞肺癌にわけられます。非小細胞肺癌はさらに腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌などにわけられます。
肺癌の60%を占めるのが腺癌で女性に多く、症状が出にくいという特徴があります。次いで扁平上皮癌で喫煙者に多いという特徴があります。
肺癌は早期の場合は症状が出にくく、風邪だと思われたりで気づかれない事が多いです。
肺癌にみられる主な症状は咳、呼吸困難、息苦しさ、息切れ、体重減少、胸の痛み、血痰などです。
肺癌は他の癌と比べて血管やリンパ管が豊富な事もあり、転移しやすいといわれています。中でも脳に転移しやすい傾向があります。
最初の治療で完全に癌細胞が取り除けなかった場合には残った癌細胞が増殖し、血管やリンパ管の流れに乗って転移し、その場所で再発を起こす事があります。
肺癌の治療法には複数の種類があり、患者や癌の状態によって適切な内容が検討されます。検討の際には医学的な有用性だけでなく、患者の希望も大切な要素です。主治医やサポートチームが一丸となって治療内容をプランニングしていきます。
肺がんの治療法は、組織型や病期ごとの標準治療に基づいて、体の状態や年齢、本人の希望なども考慮しながら担当医と共に決めていきます。複数の治療法を併用することもあります。
非小細胞肺癌が比較的早期に発見された場合、手術を中心とした治療プランを組むのが一般的です。また、再発リスクを低減させるために、術後の薬物療法も検討されます。
ただし、患者の年齢や健康状態によって「手術に耐えられない」と医師が判断すると、外科的治療でなく放射線療法が選択される場合も。
その他に、状況に応じて放射線療法や化学療法が組み合わされます。EGFR、ALK、ROS1、METなどの遺伝子変異がある場合は、分子標的薬が選択され、進行例では免疫チェックポイント阻害薬の使用も一般的です。
小細胞肺癌の場合、抗がん剤などを用いる薬物療法が中心です。ただし、発見時期が十分に早い段階であれば、手術による癌の切除も検討されるでしょう。
限局型など癌の種類や患者の状態によっては、放射線療法が併用されるケースもあります。進展型では免疫チェックポイント阻害薬(アテゾリズマブ、デュルバルマブなど)を併用した化学療法が標準的に用いられます。
肺癌治療では、治療によって妊娠や出産に悪影響が及ぶリスクがあります。そのため、妊娠中の女性や妊娠・出産を計画している女性、同様にパートナーの妊娠を希望している男性は、事前に主治医と治療プランを相談するようにしてください。
がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合には、妊よう性温存治療(妊娠するための力を保つ治療)が可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。
肺癌のステージやサイズ、発生部位によっては、手術によって癌を切除する外科治療が検討されます。ただし、手術が可能かどうかは患者の呼吸機能や年齢、全身状態なども総合的に評価して判断されます。また、特に喫煙者の場合、術後の回復をスムーズに促すためにも事前準備として1ヶ月以上の禁煙が必要です。
手術は、Ⅰ期、Ⅱ期の非小細胞肺がんと、Ⅰ期、ⅡA期の小細胞肺がんが対象で、がんを完全に切除できる場合に行います。手術の可否は術前検査での肺機能や合併症の有無などを含めて判断されます。
従来の肺癌手術では、胸部を切開して肋骨を開き、必要な組織を切除する開胸手術が主流でした。一方、現在は胸腔鏡(VATS)やロボット支援手術を活用した低侵襲手術も普及しており、術後の痛みや回復時間の軽減が期待されます。どのような手術方法を採用するかは主治医や病院の判断に基づきます。
手術の方法としては、これまで胸部を大きく切開する開胸手術が一般的でしたが、現在では胸腔鏡下手術やロボット支援下手術が増えています。それぞれに長所と短所があり、がんの位置や広がり、患者の状態により適した手術法が選ばれます。
肺葉切除術は、主にⅠ期からⅡ期の非小細胞肺癌に対する標準的な手術です。癌が存在する肺葉を手術によって除去し、同時にリンパ節郭清を行うのが一般的です。がんが周囲の組織に浸潤している場合には、胸壁や心膜も併せて切除されることがあります。
切除範囲は癌の大きさや局在によって決まり、術前の画像診断や肺機能検査による評価が重要です。術後の肺機能低下を見越したリハビリ計画も必要です。
縮小手術では、肺機能を可能な限り温存するために、肺葉の一部だけを切除します。適応はごく早期の非小細胞肺癌や、高齢・合併症のある患者など、標準術式が困難なケースです。
縮小手術は肺機能を温存できる反面、再発リスクがやや高くなる傾向があり、適応は慎重に判断されます。代表的な方法には「区域切除」と「楔状切除」があります。
左右一対の肺のうち、癌が発生している側の肺を丸ごと切除する術式です。肺葉切除術で癌を取りきれない場合や、気管支・大血管への浸潤がある場合に検討されます。胸壁や心膜の合併切除が伴うこともあります。
再発リスクを抑えられる反面、肺機能への負担が非常に大きくなるため、心肺機能や年齢を含めた厳格な術前評価が不可欠です。
手術によって肺を部分的または全体的に切除すると、肺活量の低下、術後の肺炎、無気肺、縦隔の癒着など、さまざまな合併症のリスクがあります。
合併症の発症リスクは手術の種類や切除範囲により異なりますが、術前からの呼吸リハビリや体力維持が、術後回復を左右する大切な要素です。
特に、肺活量の低下によって呼吸機能が落ちると、咳がしにくくなり痰や唾液が気道に留まりやすくなるため、誤嚥や肺炎を防ぐための呼吸訓練が重要になります。
肺の手術後には肺活量が低下し、痰を出しにくくなることで肺炎や無気肺を起こすリスクが高まります。これらを防ぐため、手術前から呼吸訓練を行うことが勧められています。術後のリハビリをスムーズに進めるためにも、術前に呼吸法や体力づくりを行い、医療スタッフのサポートのもとで術後回復を促進しましょう。
肺癌では、高エネルギーの放射線を照射して癌細胞を殺し、癌を退縮させる放射線療法も採用されます。
放射線療法は癌の進行を遅らせるだけでなく、症状の緩和や延命を目的として使用されることもあります。また、放射線と細胞障害性抗がん薬を併用する「化学放射線療法」も、高い効果が期待できる治療法です。
化学放射線療法は副作用リスクも伴うため、患者の体調や呼吸機能を踏まえ、主治医による慎重な判断が必要です。
非小細胞肺癌に対しては、手術が難しい場合や患者が手術を希望しない場合に放射線療法が選択されます。特に、定位放射線治療(SABRまたはSBRT)は、がん病巣を狭い範囲に集中して照射できるため、Ⅰ期の早期がんに対して外科手術と同等の効果があるとされます。
Ⅱ期・Ⅲ期では、体の状態が良好であれば化学療法と組み合わせた化学放射線療法が行われ、治癒を目指した治療になります。治療効果や副作用をみながら、治療終了後には免疫療法(ドゥルバルマブ)による維持療法を追加するケースもあります。
Ⅰ期からⅢ期で手術が難しい場合には、治癒を目標とした放射線治療を行います。Ⅱ期・Ⅲ期で体の状態がよい場合には、化学放射線療法を行います。また、Ⅰ期・Ⅱ期で医学的には手術が可能でも、患者本人が手術を希望しないときには、治癒を目標とした放射線治療を行うことがあります。
限局型の小細胞肺癌では、化学療法と放射線治療を併用する「同時化学放射線療法」が標準治療です。初回治療によってがんが縮小し、状態が良好であれば、脳への転移を予防するための予防的全脳照射(PCI)が行われる場合もあります。
進展型の場合でも、症状緩和を目的とした放射線治療(骨転移による痛みや脊椎圧迫に対する照射など)が行われることがあります。
Ⅰ期で手術ができない場合や、Ⅱ期以降でも体の状態がよい場合には、化学放射線療法を行います。また、Ⅰ期またはⅡA期以外の限局型では、初回の治療によってがんが画像検査では分からないほど縮小し、体の状態も良い場合には、脳への転移による再発を予防するために脳全体に放射線を照射することがあります(予防的全脳照射)。
細胞分裂が盛んな組織は放射線の影響を受けやすく、放射線照射によって炎症などの副作用が生じることがあります。
肺癌に対する放射線療法では、食道や気道粘膜への影響により、嚥下困難や咳、発熱、息苦しさなどが見られることがあります。また、放射線性肺炎(放射線肺臓炎)や、皮膚炎、だるさ、倦怠感も一般的な副作用です。
副作用の出現は照射範囲・線量・照射回数によって異なるため、異変を感じた際は早めに主治医へ相談することが重要です。
肺癌では主として「細胞障害性抗がん薬」「分子標的薬」「免疫チェックポイント阻害薬」といった薬剤を使う薬物療法が行われます。
薬剤は肺だけでなく血流によって全身を巡るため、肺以外の臓器へ転移が疑われるような場合でも治療効果を期待できるのがメリットです。そのため、外科治療や放射線療法と組み合わせて薬物療法が採用されることも少なくありません。
ただし、薬物療法は副作用が生じやすいので、状況によっては異なる薬剤が再検討。患者の状態に合わせて細かく調整していきます。
細胞が増殖する仕組みそのものを阻害して、癌細胞の増殖を抑える薬剤です。非小細胞肺癌・小細胞肺癌いずれの治療にも広く使われており、プラチナ製剤(シスプラチン、カルボプラチン)やタキサン系(パクリタキセル、ドセタキセル)などが代表例です。
正常な細胞にも影響を及ぼすため、脱毛や骨髄抑制、吐き気などの副作用が現れることがあります。
癌細胞が特徴的に有している分子をターゲットとして、癌細胞を狙って攻撃する薬剤です。非小細胞肺癌では、EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子、ROS1、RET、MET、BRAFなどが治療対象となります。
チロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)やALK阻害薬などは、遺伝子検査の結果に基づき選択され、進行期では一次治療薬として使用されます。
肺がんでは、チロシンキナーゼ阻害薬や血管新生阻害薬を使用します。がんの原因となっている遺伝子変異を調べ、その変異に適した薬剤を使用することで高い効果が期待できます。
通常、体内の異物や病原菌などは免疫細胞によって攻撃されますが、癌細胞は免疫の監視を逃れる性質を持つことがあります。
免疫チェックポイント阻害薬は、癌細胞が免疫から逃れる仕組みを妨害し、免疫によって攻撃させる薬剤です。非小細胞肺癌に対してはニボルマブやペムブロリズマブ、小細胞肺癌にはアテゾリズマブやデュルバルマブが使用されます。
免疫療法は近年の肺癌治療において非常に重要な役割を担っており、遺伝子変異がない症例に対しても有効性が確認されています。
免疫療法は、免疫の力を利用してがんを攻撃する治療法です。肺がんの治療では、免疫チェックポイント阻害薬が効果を証明されており、進行例や再発例を中心に広く使用されています。
非小細胞肺癌に対する薬物療法では、がんの進行度や遺伝子変異、PD-L1の発現状況などにより、細胞障害性抗がん薬・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬のいずれか、あるいは組み合わせて使用されます。
術後補助療法や再発・進行例に対して、治療効果・副作用・患者の全身状態を評価しながら柔軟に薬剤選択が行われます。
限局型の小細胞肺癌では、化学放射線療法が主な治療となります。進展型では、細胞障害性抗がん薬に加えて、免疫チェックポイント阻害薬を併用する治療法が標準とされています。
代表的なレジメンとしては「カルボプラチン+エトポシド+アテゾリズマブ」や「デュルバルマブ併用」などが挙げられます。
進展型は主に細胞障害性抗がん薬で治療します。免疫チェックポイント阻害薬と併用することもあります。使用する薬は健康状態や年齢によって異なります。
薬物療法によってどのような副作用が生じるかは使用する薬剤や患者の体質などによって異なります。
細胞障害性抗がん薬では脱毛・吐き気・白血球減少などが一般的で、分子標的薬では皮疹や下痢、肝機能障害などが見られることがあります。免疫チェックポイント阻害薬では、自己免疫性の副作用(間質性肺炎、甲状腺炎、大腸炎など)も報告されています。
副作用の出現状況に応じて薬剤の中止や変更、支持療法の併用が検討されるため、定期的な診察や血液検査によるモニタリングが欠かせません。
使用する薬剤の種類によって副作用は異なり、その程度も個人差があります。細胞障害性抗がん薬は新陳代謝の盛んな細胞に影響を与えやすく、脱毛や、口内炎、下痢、白血球や血小板の数が少なくなる骨髄抑制などの症状が出ることがあります。
緩和ケアとは、癌の消滅や根治そのものを目的とした治療法でなく、癌による肉体的な苦痛や精神的ストレスなどの負担を緩和・軽減して、患者が毎日を意欲的に過ごせるようにサポートしていくための治療法です。また、生活の質(QOL)の維持・向上を目的とした治療法としても検討されます。
肺癌の治療では手術によるダメージだけでなく、放射線療法や薬物療法による副作用もあり、転移についても注意しなければなりません。そのため、可能な限り肺癌の痛みや治療に伴う苦しみを緩和して、患者自身が前向きになれるようサポートするのが重要。
緩和ケアは肺癌と診断された時点からプランニングしていくことが望ましいと言われています。患者の希望やライフスタイルを考慮しながらオーダーメイドの治療内容を構築していくのが緩和ケアのポイントです。
なお、特に癌治療や癌そのものによる副作用・合併症・後遺症を予防するための治療は「支持療法」と呼ばれます。
治療や療養生活を送る患者さんの肉体的、精神的、社会的、経済的、すべてを含めた生活の質を意味します。病気による症状や治療の副作用などによって、患者さんは治療前と同じようには生活できなくなることがあります。QOLは、このような変化の中で患者さんが自分らしく納得のいく生活の質の維持を目指すという考え方です。治療法を選ぶときには、治療効果だけでなくQOLを保てるかどうかを考慮していくことも大切です。
癌検診の目的は、いうまでもなく癌の早期発見・早期治療開始によって癌による死亡を減らすことです。日本では、厚生労働省が定める「がん予防重点健康教育およびがん検診実施のための指針(平成28年一部改正)」で検診方法が提示されています。
40歳以上の人は、年1回の肺癌検診を受けることをおすすめです。自治体のほとんどが公費で検診費用の大半を補助しており、住民の皆さんは一部の自己負担だけで検診を受けられます。
検診の内容は肺のレントゲン検査と問診、50歳以上で喫煙指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が600以上の人は喀痰細胞診が加わります。問診では自覚症状の有無や喫煙歴、妊娠の可能性、過去の検診の結果などを確認します。検診の結果「要精密検査(癌の疑いあり)」とされた場合は、医療機関において精密検査を受けることになります。
厚生労働省の指針では、癌の死亡率減少効果が確実視され、偶発症や過剰診断、偽陰性・偽陽性といった不利益の少ない検査方法だけが癌検診として推奨されています。肺癌検診の内容が現時点で肺のレントゲン検査と喀痰細胞診だけなのは、そういった理由があるためです。
なお、検診はその時点で症状もなく健康な人を対象に実施されるもの。癌の治療歴があって何らかの症状がある場合は、まずは主治医に相談してください。もちろん、治療後の経過観察期間中も主治医の指示に従う必要があります。
肺癌を再発させないためには生活習慣を改善させる事が重要です。
食生活の見直しや運動を行う、ストレスを溜めないという事が重要ですが、肺癌の場合は何と言っても喫煙が大きく影響します。
禁煙する事はもちろんのこと、身近な人の喫煙による副流煙も肺癌のリスクを高めるので注意が必要です。
また手術後の術後補助療法は再発のリスクを大幅に減らす事が出来る治療方法です。癌が再発した場合は、癌治療専門病院へ行き、早めに適切な治療を行う事が重要です。
ここではステージごとの肺癌の状態について解説しています。
| Ⅰa期 | リンパ節への転移は見られず、癌の大きさが直径3㎝以下の状態。 |
|---|---|
| Ⅰb期 | リンパ節への転移は見られず、癌の大きさが直径3~5㎝、あるいは3㎝以下で胸膜に達している状態。 |
| Ⅱa期 | 癌の大きさは3~5㎝で、気管支周辺や肺門、肺内のリンパ節への転移が見られる状態。 あるいはリンパ節への転移は見られないが癌の大きさが直径5~7㎝の状態。 |
| Ⅱb期 | 癌の大きさが5~7㎝で、気管支周辺や肺門、肺内のリンパ節転移が見られる状態。 あるいはリンパ節転移は見られないが、癌の大きさが7㎝を超え、胸壁や横隔膜、胸膜などに達している状態。 |
| Ⅲa期 | 縦隔や器官分岐部のリンパ節に転移が見られ、癌の大きさが7㎝以下の状態。 あるいは気管支周辺や肺門、肺内のリンパ節に転移が見られ、かつ癌の大きさが7㎝以上、胸壁や横隔膜などに達している状態。 またはリンパ節への移転は見られないが、癌が縦隔や心臓、食道などに達している状態。 |
| Ⅲb期 | 癌の大きさや浸潤度に関係なく、癌のある側の肺と反対側の縦隔、肺門、前斜角筋、鎖骨上窩のリンパ節への転移が見られる状態。 |
| Ⅳ期 | 癌の大きさや浸潤度、リンパ節転移の有無などに関係なく、癌の遠隔転移が見られる状態。 |
肺がんのステージ分類は、癌の大きさと浸潤度(T因子)、リンパ節転移の有無(N因子)、遠隔転移の有無(M因子)の3つの因子から総合的に判断。いずれの場合も数字が大きくなるにつれ、また同じ数字内でも「a<b<c」の順で重度となります。
体の状態なども考慮して、切除手術が可能と判断されれば、肺にある癌(原発巣)と転移した癌(転移巣)とを全て切除し、転移していると考えられるリンパ節も全て切除します(リンパ節郭清)。術後は薬物療法で経過を観察します。
手術は不可能と判断された場合には、放射線療法で癌細胞を攻撃。化学療法と併用する場合もあります。
Ⅲ期でも放射線療法では効果が得られないと判断される場合や遠隔転移が見られるⅣ期では、抗がん剤や分子標的治療薬などの薬物療法を実施。また、脳転移や骨転移による症状を緩和させる目的で、緩和的治療も行われる場合があります。
一方、肺がんとしては稀な種類である「小細胞がん」というものもあり、これは進行が早く遠隔転移しやすいものの、抗がん剤や放射線療法が効きやすいため、Ⅱ期であっても手術ではなく下顎放射線療法や薬物療法がとられることがあります。